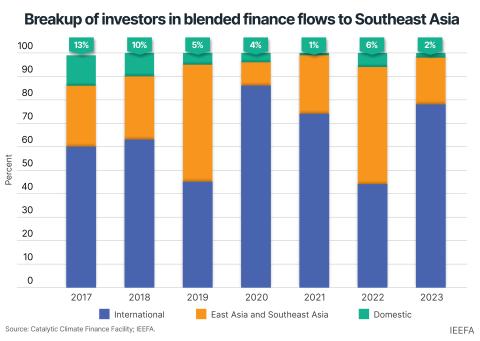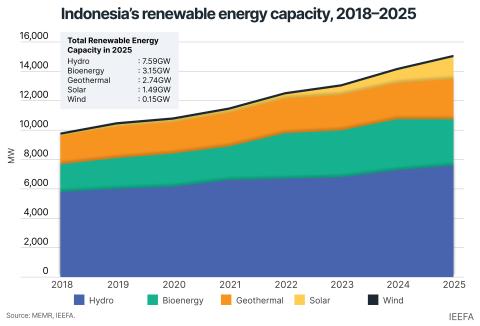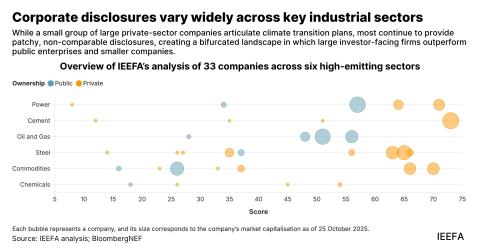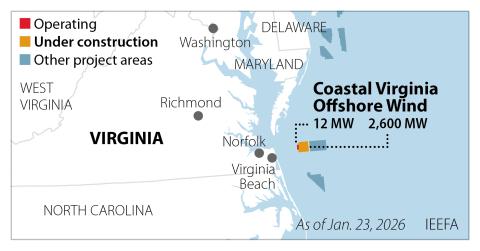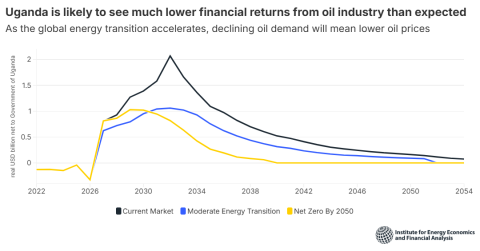日本の再エネ導入拡大の主な障壁

Key Findings
近年、日本の再生可能エネルギー導入の増加ペースは鈍化し、日本の再エネ導入目標との差を広げており、2030年までに総発電量に占める再エネ比率を36〜38%に引き上げ、2050年までにカーボンニュートラルを実現するという目標の達成に関する懸念が高まっている。
国内の発電設備容量の約75%を占める大手電力会社は、国内における再生可能エネルギーへの投資を最小限に抑え、化石燃料および原子力の電源を優先している。供給電力の非化石電源比率を44%以上にするという目標の義務づけが、十分に徹底されていないことがこの傾向をさらに強めている。
福島県や秋田県における地域主導の取り組みは、再生可能エネルギー導入を加速させる有効なモデルとなっている。送電規制および財政支援の改革、地域主体の再エネ導入ゾーニング計画への支援、電力購入契約(PPA)の活用を促進し、都市と地方の再生可能エネルギー開発格差の是正を行うことによって、これらの取り組みを全国的に広げていくことが可能である。
一般電気事業者が再生可能エネルギーへの投資に消極的であることや非化石証書(NFC)が十分に活用されていないことに加え、系統制約や出力制御、さらには財政的、規制的な送電枠組みの欠如などといった構造的課題が、日本の電力システムへの再エネの統合を妨げている。
要旨
日本の再生可能エネルギー導入は、目標と実績の差が広がりつつある。日本では、2012年に固定価格買取制度(FIT)が導入以降、再生可能エネルギーの設備容量は大幅に増加したものの、導入ペースが減速している。そのため、2030年までに電源構成の再エネ比率を36〜38%に引き上げ、2050年までにカーボンニュートラルを実現するという目標を達成できるか否か、懸念が強まっている。
化石燃料推進派は、再生可能エネルギーでは安定したエネルギー供給を確保できないと主張し、それを理由に化石燃料、とりわけ液化天然ガス(LNG)への依存の継続を正当化している。最新の第7次エネルギー基本計画においてもこの見方が反映されており、再生可能エネルギー導入拡大が停滞した場合LNGの輸入量が増加するシナリオを含んでいる。
構造的かつ制度的な問題が日本の電力系統への再エネ電気の効率的な統合の障壁となっている。2010年から2023年にかけて、総発電電力に占める再エネ比率は9.5%から22.9%に上昇したが、年平均成長率は低下し、出力制御量は増加、今後の導入は不透明である。
2023年度における再生可能エネルギーの発電電力量の伸びはわずか5.9%と、2010年以来最低となり、出力制御量は過去最高の1.88 GWhに達した。これは、電力系統の柔軟性不足や供給計画の調整の脆弱性、市場の不整合に起要因する、設備容量の拡大と電力システム統合との不均衡を明確に示している。
主な構造的課題は、大手電力会社による国内再生可能エネルギー開発への消極的な姿勢である。大手電力会社は日本の発電設備容量の約75%を保有しているが、太陽光や風力といった確立された技術への投資は最小限にとどまり、化石燃料および原子力の電源を優先している。国内で進める再生可能エネルギー事業は限定的であり、むしろ海外に偏重している。規制遵守が徹底されていないことがこうした再生可能エネルギーへの移行に対する消極的な姿勢を助長している。小売電気事業者は、2030年までに供給電力量の44%を非化石電源から調達する義務を法的に負っているものの、目標未達成に対する経済的制裁はなく、市場インセンティブも不十分である。
また、電気事業者は非化石証書(NFC)制度の活用にも消極的である。これらの制度は自ら発電設備を保有せずとも調達義務を満たすことが可能にするが、実際に購入された証書の多くは、原子力など再生可能ではないエネルギー源によるものとなっている。供給量の不足や透明性の欠如も、制度の利用を阻害している。
系統接続と出力制御は依然として大きな課題である。九州や北海道といった自然エネルギー資源に恵まれた地域では、再生可能エネルギー事業者が系統接続の遅延や費用の高さに直面している。送電容量に限りがあり、また、給電ルールは火力発電所の最低出力を30〜50%としていることから、再生可能エネルギー発電の拡大はさらに制限されている。
日本には、送電網整備のための包括的な枠組みが欠けている。再生可能エネルギー発電が地方や沿岸地域に集中する一方、需要は大都市圏に偏在している。複雑な許可プロセスと送電事業者の資金不足により、長距離送電網の開発は依然として進んでいない。その結果、再生可能エネルギーの供給と需要の間に物理的、経済的ギャップが生じている。
都市と地方の格差は、再生可能エネルギー開発パターンにも反映されている。都市部が土地不足と高い事業開発費用に直面する一方で、大規模再生可能エネルギー発電設備のほとんどは地方に設置されている。各地域を結ぶためには、政策の一体化とインフラへの投資が不可欠である。
日本のいくつかの地域は、有意義な進展が可能であることを実証している。福島や佐賀、秋田、北海道などの地域では、独自で再生可能エネルギー導入目標を掲げ、地域コミュニティを巻き込み、地域資金を動員してクリーンエネルギーの拡大を支えている。こうした地方自治体の取り組みは、再生可能エネルギーの導入を拡大するとともに、他地域にも応用可能なモデルを示している。
日本は、バックアップ電源として化石燃料に頼るのではなく、こうした地域レベルの成功事例を全国に拡大していくべきである。そのための優先課題には、系統接続ルールの見直し、電力市場設計の近代化、大手電力会社に課されている非化石電源調達義務の実効性強化、および電力購入契約(PPA)を通じた再エネ導入の道筋の整備が含まれるべきである。
著者について
宮本美智代はエネルギーファイナンススペシャリストであり、アジアのエネルギー市場、特に日本を専門としている。気候変動政策や市場分析の経験を有し、日本および世界における脱炭素化の動向に強い関心を持っている。
本報告書は、IEEFAによって英語で発行された "Key barriers in Japan's renewable energy development" の日本語翻訳版です。翻訳には十分配慮しておりますが、内容の正確性・完全性を保証するものではありません。解釈に疑義が生じた場合や正確な参照・引用を行う際は、必ず英語原文をご参照ください。